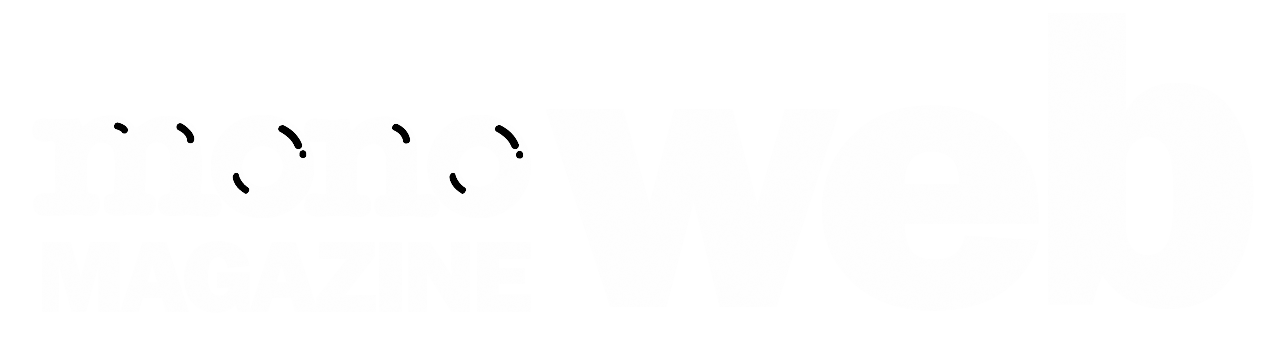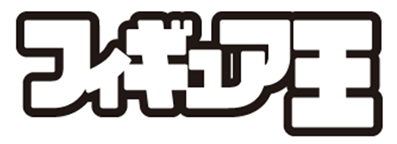ダイナースクラブのツアーが開催された、鎌倉時代に建立された建長寺。
新年の初詣、おせち料理など、日本の伝統行事を満喫することが何かと多いこの時期。日本ならではの名所に出かけて、崇高な気分に浸りたいなんて思っている人も多いのではないだろうか。
そんな今紹介したいのが、日本初のクレジットカード 「ダイナースクラブ」が、寺社仏閣を貸し切って行うカード会員向けの境内参拝ツアー。
昨年11月には、日本で最初期の本格的な禅寺として名高い、北鎌倉「建長寺」が特別に貸し切られ、僧侶による案内のもと境内参拝ツアーが実施された。
日本で最初に建てられた「禅の専門道場」だったとも言われる建長寺。ツアーに参加することができたので、その様子をお届けしよう!

案内をしてくれた建長寺内務部の三ツ井宗司さん。
そもそも建長寺は、禅宗寺院を代表する鎌倉五山第一位のお寺とされ、鎌倉幕府5代執権・北条時頼が、中国(南宋)の禅僧である蘭溪道隆を招き、建長5年(1253年)に創建した古刹だ。

建長寺の境内に入るとまず最初に現れるのが、シンボル的存在ともいえる大きな門を構える「三門」だ。高さ20mにもなる三門の楼上には五百羅漢が安置されている。
スタートは、国の重要文化財にも指定されている「建長興国禅寺」の大扁額がかけられた「三門」から。
「三門」とは、「三解脱門」の略で、空、無相、無作を表し、執着から解き放たれることを意味する。楼上には、釈迦如来・五百羅漢・十六羅漢が安置され、その下を通ると心が清浄になるといわれているのだ。
建長寺の主な建物は、禅宗寺院の特徴で、背骨のようにまっすぐ一直線上に奥へ奥へと建てられていて壮観だ。

重さ2.7tからなる大きな鐘には、開山の大覚禅師(蘭溪道隆)の銘文を撰している。
境内を進んだ先にあるのは、1255年(建長7年)に、関東の鋳物師の筆頭だった、物部重光によって鋳造された梵鐘。創建当時のままの国宝の釣り鐘だ。
明治28年にかの夏目漱石が、「鐘つけば銀杏ちるなり建長寺」と詠んだとされ、親友である正岡子規がこの句を参考に、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」と詠んだことでも、知られている。

「嵩山」の額が掲げられた山門が薬医門。傾斜が緩やかな坂を登った先に、最高聖地とされる「西来庵」が存在する。
先へ進むと薬医門と呼ばれる西来門がある。この門の奥にあるのが、通常は非公開とされている、建長寺の最高聖地「西来庵」だ。

通常は非公開の「西来庵」を、特別に眺めることができた。
開山堂の背後には、蘭渓道隆の墓(大覚禅師塔)と円覚寺開山の無学祖元の墓があるそうだ。

仏殿はよく見ると、装飾や絵が女性的でどことなく柔らかな印象を受ける。
そして次にたどり着いたのが、国の重要文化財にも指定されている仏殿。現在の仏殿は、徳川家光の母、お江の方の霊廟で、芝の増上寺から1647年(正保4年)に移築されたものとされている。

内部はすべて漆塗で、華麗な装飾が施されているのが特徴だ。本尊は地蔵菩薩坐像。

もともと住職が説法をする場所だった法堂は、現在はお参りができるようになっている。
法堂には、千手観音とパキスタンより寄贈されたという釈迦苦行像が安置され、現在は大きな行事に使われている。

縦10m×横12m、畳約80畳分にもなる巨大な雲龍図。五爪の龍が厳かでとても美しい。
さらに天井には、小泉淳作氏の大作である巨大な雲龍図が高々と掲げられ、見るもの全てを圧巻する。

仏殿への参道には、樹齢750歳以上といわれる立派なビャクシンの木が植えられている。

方丈(龍王殿)の正面に位置している豪華な唐門。
僧侶の案内のもと、国重要文化財である仏殿、法堂に続き、唐門も見学することができた。この煌びやかな唐門は、仏殿同様、増上寺のお江の方の霊廟前にあった門を移してきたものといわれている。2011年に大修理が終了して、建立当時の姿になったそう。

本堂にあたる龍王殿(方丈)で、坐禅を体験する。
禅の源流たる建長寺で、姿勢を正して坐った状態で精神統一を行う禅の修行法のひとつである坐禅を体験する。鼻からゆっくり息を吸い、静かに息を吐く、本格的な坐禅を約40分間行うことができた。

大広間で特別法話を講演した、僧侶の松本隆行さん。

ダイナースクラブ代表取締役社長 五十嵐幸司氏も登壇し挨拶を述べた。
坐禅体験の後、僧侶から特別法話を聞くことができた。江戸時代から語り継がれてきた貴重な法話は、今聞くからこそ学びも多く、心が洗われる想いだ。


約20分の写経体験。文字を書く機会が少なくなった今だからこそ、精神を統一して行うことで晴れやかな気分になれる。
仏教の経文を書き写す修行のひとつである、写経も体験できた。一字一字丁寧に写経することで、体と呼吸、そして心を調えることができる。

八寸、坪、木皿、汁蓋、平椀、親椀、食事、お椀、甘味から成る精進料理。
イベントの最後には、精進料理を味わうことができた。胡麻豆腐や麩、湯葉差し、いろどり野菜の白和え、京がんも、季節の野菜など様々な自然の恵みを食すことができた。

建長寺発祥の「建長寺汁」→「けんちん汁」になったと伝えられている。
中でも美味しいけんちん汁は、建長寺が発祥といわれている。野菜を油で炒めてから煮込む手法は、当時の日本にはなく、中国の禅僧がもたらした大陸の文化がルーツになっているそうだ。
鎌倉時代に建長寺は、こうした食はもちろんのこと中国大陸からもたらされた、最先端の学問や技術・文化を学ぶことができる、国際的なキャンパスのような場所だったと考えられる。
建長寺の境内の一角では、現在も全国から集まった禅宗の修行僧たちが、昔と変わらない厳しい修行を行なっており、また、創建当時から大切に伝えられてきた宝物は、毎年11月の「宝物風入れ」で見ることができるそう。
ダイナースクラブでは、会員を対象に毎年秋に、こうした古刹を巡る境内参拝ツアーを実施しているので、今後是非参加してほしい。
建長寺は一般の人でも、坐禅や法話に参加したり、年間を通じて法要や様々な行事に参加できるお寺なので、北鎌倉エリア散策の際に訪れてみてはいかがだろう。
問い合わせ
ダイナースクラブ
建長寺
最寄り駅:JR横須賀線 北鎌倉駅 徒歩15分
拝観時間:8:30〜16:30