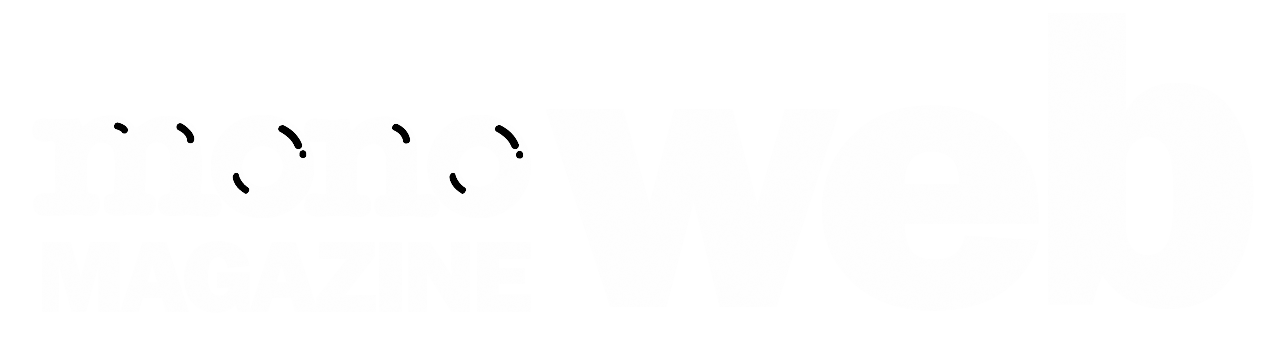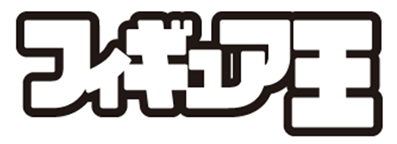特許と言えば、米国特許庁(USPTO)の長官が述べているように「新しいアイデアや、技術革新や創造性への投資を守るためのメカニズム」として「最新鋭のテクノロジーの進化や成果を見守る」ためのモノである。つまり、発明者の権利を一定期間守ることで、科学の革新や社会の進化を促すという大きな役割をもっている。だが、一方で、米国特許庁で昔に出願された特許を見ていくと、中には、おかしな、おかしな特許をたくさん発見できる。今回は、そんな、はたから見たらかなりおかしい特許を図面とともに紹介する。当時の世相を反映するような発明、時代が違うからこその発明、現代社会にも通じる部分があるのではないかと思われるような発明。ちょっとおかしな発明を通して、アメリカ社会をおもしろおかしく見てみるのはどうだろう。
構成/ワールド・ムック編集部 文/伊藤浩子
※米特許図面をもとに編集部が色を付けました。

ゆらゆら揺れるバスタブ
(1900年認可)
1900年に認可されたこのゆらゆら揺れるバスタブの特許。バスタブが波間を進む船のように前後方向に上下に揺れることによって、バスタブ内のお湯がジャバジャバと入浴中のユーザーの体にかかる仕組みとなっている。なぜ、体にかかるようにわざわざバスタブを揺らすのか? その理由については詳しく書かれていないが、どうも当時はやっていた健康法に由来するらしい。病院や療養所または自宅などで、医療従事者が治療中に使用するため、と記されている。ちなみに、現在、イギリスでは、「ハンモックバス」なるハンモック型のバスタブが本当に販売されているようだ。

ハンティング用デコイ
(1897年認可)
ネブラスカ州の住人ジョン・シーバーズ・ジュニアが考案したのは、獲物に気づかれないための、中が空洞な動物型のデコイで、ハンターたちはこのデコイの中に身を隠して、獲物に近づく、というもの。動力源はなく、ハンターたちは、動物の脚に入って自らの脚で移動する。獲物に気づかれないようにじゅうぶん近づいたら、デコイの頭部をパカっと開け、そこから銃を撃つのだ。移動中には折りたたんで小さくして収納可能ということだが、人ふたりが入るからには、サイズもそこそこ大きいはず。はたして本当に獲物に気づかれずに近づけるのか謎は残る。

フープ状のおもちゃ
(1963年認可)
フープひとつ。特許を取得できるような斬新な発明なのか?と思うようなこの特許だが、実はフラフープ®の世界的ブームを巻き起こしたアメリカのワムオー社の共同経営者アーサー・メリン氏が出願したもの。フープ状のおもちゃは古代ギリシャより、ツル状の植物を輪っかにしたものが存在し、メリン氏自身、オーストラリアを旅行中に子供たちが竹製のリングで遊んでいるのを見てフラフープを思いついた。1957年の発売後、4ヵ月で2,500万本のフラフープが売れ、2年間で1億本も売れたという。このフラフープ1本によって、ワムオー社の運命が大きく変わったのである。フラフープの商標登録は1960年に認可されているが、フラフープの発売から6年経ってようやくこの特許が認可されたという点が興味深い。

寝ている人を起こす装置(1882年認可)
アラーム時計の音に慣れてしまい、なかなか起きられないという人のための発明。寝ている人を起こすためのシンプルで効果的な装置とうたわれている。その仕掛けは図を見れば分かる通り、寝ている人の頭上にブロック状のものを複数ぶら下げておき、あらかじめセットしておいた時間になると、それが顔面に落ちてくる、というものだ。発明者によると、ぶら下げるものは、寝ている人が目を覚ますくらいの刺激になるが、そこまで痛くないものがいいそうだ。痛みの感じ方は人それぞれなので、本当に痛くないかかなり心配だ。

ニワトリ自動消毒装置(1919年認可)
ニワトリに消毒用の粉末または消毒液をかける完全自動化装置。NY在住のフィンランド人が発明したそうだが、消毒作業は完全に自動化されていて、養鶏所の人の手を借りない点がウリ。使い方は、この自動消毒装置を、ニワトリが必ず通る養鶏所の入口や通路に設置しておく。ニワトリが装置に乗ると、噴射装置が作動して、消毒剤が噴射される。ニワトリが通るだけで前も後ろも消毒可能という点がすばらしい。

ゴルフクラブ(1905年認可)
「ものすごく正確」なパットが打てるとうたっているのがこちらのゴルフクラブ。正確に言うと、パターなのだが、その見た目がなんとも斬新! 柄の部分が二股に分かれ、その先端部分にはプレーヤーの肘あたりに固定することができるような取っ手がついている。取っ手をしっかりと腕に固定することで、完璧なスイングができるというのだが。現在、このパターが普及をしていないところを見ると、ショットはそれほど正確にはいかなかったのか。

歯用プロテクター(1962年認可)
このフットボールプレーヤー向けマウスピースのスゴイところは、マウスピースが必要ない時には、口から簡単に吐き出して外すことができる点だ。吐き出したマウスピースはどこにいくか? マウスピースは紐のようなものでフェイスガードについているので、外しても目の前にブラブラしている。だから、なくすこともないし、また簡単に口の中に入れることができるという。万が一、激しい衝撃が加わってノックダウンされたとしても口から飛び出たマウスピースがどこに飛んでいったか探す必要もない。こちらもまた実用化された形跡はない。

帽子ガード(1914年認可)
帽子をかぶるのが身だしなみとされていた時代ならではの発明がこちらの帽子ガード。人が大勢集まる場所で、同じような帽子をかぶる人が多かったため、誤って人の帽子をかぶって帰ってしまうことが多かったのだろう。使い方は、帽子の内側の汗止めと帽子本体の間に、この小さな装置を設置する。帽子の持ち主は、帽子を脱いでどこかに置く時に、この装置の金具が飛び出た状態にする。すると、誤ってかぶってしまった人が即座に違和感を感じるという。さらに、帽子を盗もうとする人にとっても、このメカニズムを解除しなければ帽子をかぶることができない。ただ、みんながこの装置を帽子に取りつけたら、やはり見分けはつかないような気がする。

口ひげガード(1889年認可)
口ひげを蓄えるのが男性の一般的な身だしなみとされていた19世紀終わりに、多くの男性を悩ませたであろう、スープを飲む時に口ひげにスープがついてしまう問題。これを解決するために考案されたのが、この口ひげガードなるアイテムだ。スプーンに取りつけることで、スープを飲むたびに口ひげがスープに浸ってしまい、びしょびしょになるのを防いでくれる。何かをかき混ぜる時にはガード部分を上げて使用することができるので邪魔にならない。

ベビーカー・子供用キャリー(1884年認可)
こちらは、子供または人形を運ぶためのベビーカー。靴の形をしていて、軽量で扱いやすいが、しっかりとしていて頑丈であるとしている。発明者のこだわりは、その形。できれば靴の形をしているのが望ましいとしており、なぜか靴の形にこだわっていたことがうかがい知れる。靴の前部分は開く仕様になっているが、留め具としては靴紐に似たような紐が好ましいとしている。イラストのように、傘をつけることもできる点がすばらしいが、やはり実用性を考えるとなぜ靴の形なのだろうかと疑問が残る。

腹話術用の人形(1941年認可)
これは厳密にいうと意匠で出願された特許であるが、イラストがあまりにインパクトがあるので選んでみたもの。1940年という世界情勢が不安定な時代に出願された、あまりにこっけいな人面鳥の人形の頭部分のデザイン。どういう目的で発明者がこのデザインを思いついたのかは不明だが、1941年に無事に認可されている。

シェービング用ゲージ(1923年認可)
自分でもみあげを剃るのが難しい、そんな人の悩みを解決しようと発明されたのが、こちらのシェービング用のゲージである。使い方は簡単。耳の後ろに本体をひっかけて、ゲージからはみ出た部分の毛をカミソリでなぞって剃るだけ。ガイドに沿って切るので、きっちりとそろった直線にカットできるほか、右耳と左耳で同じ高さにそろえることができ、また、ゲージ本体の長さをカットすることでもみあげの長さを調節することが可能。

アニマルトラップ(1927年認可)
この発明は、ネズミ捕りの装置に関するもので、メーソンジャーと呼ばれる食品を入れるための広口密閉式ガラス瓶に取りつけて使用するもの。ネズミは餌を求めてガラス瓶の中に入るが、この装置のおかげで、一度入った瓶から外に出ることができない。瓶の中に入ったねずみは、いつでも出られると錯覚し、出ようと試みてもまた元の場所に戻ってしまうがそのこと自体に気づかないらしい。万が一、無限ループの中にいると気づいたとしても、出られない仕組みになっていて、同じねずみで数回実験を繰り返しても、喜んでまた瓶の中に入っていたそうである。

かくはん機、洗濯機に応用可能な装置(1888年認可)
こちらの発明は、ブランコをこぐとその前後運動が回転運動へと変換され、かくはん機や洗濯機などに応用できるというもの。図面で記されているのは、女の子がブランコを漕いでいて、その横にある洗濯機が回るというひとつの応用例。かなりサイズは大きいが、現代でいうところのハンディーフードプロセッサのようなものだろうか。1888年当時としては斬新なアイディアだったと思われる。

乳業家向けマスク(1919年認可)
こちらの発明では乳しぼりをする酪農家が直面するゆゆしき問題を解決しようと試みている。それは、とくにハエが多く発生するシーズンに、牛のしっぽが顔を直撃するのを防ぐというもの。細かい網をめぐらした特製マスクをつければ、牛のしっぽや毛が顔面に当たるのを防ぐことができるのだ。特許には、これで牛も自由に尻尾を振り回すことができ、問題解決になることまちがいなしとうたわれている。

釣り具(1894年認可)
釣りを楽しむ人用に発明されたこちらの釣り具は、餌をつけた釣り糸に円形または楕円形の鏡を取りつける、というアイデアをウリにしたもの。餌に寄ってきた魚が鏡に映った自らの魚影を見て、ほかの魚と勘違いし、その結果、ほかの魚に餌をとられまいと普段よりも警戒心を解いて慌てて餌に食いつくだろう、と説明している。はたして、本当に簡単に魚が餌に食いつくのか? このしかけで本当に魚が警戒心を解くのか、興味深い。

列車の中で快適に寝ることができるハンモック(1889年認可)
普通列車で長旅をすることが多かった1800年代後半に考案されたこのハンモックは、寝台列車に乗れない人たちが、普通列車の座席と座席の間につるして使うとされている。使うのは前の座席と自分の座席。つまり、前後の座席にひっかかるようになっており、前方に脚を支えるロープが設けられているので、フットレスト的な機能を合わせもっている。なんとかして旅を快適にしようというナイスな発明だ。

酒用フラスク(1885年認可)
1800年代後半はフラスクボトルに高アルコール度数のお酒を入れて持ち歩いて飲むことがポピュラーだったようで、こちらの発明では、フラスクであることを周囲に悟られない工夫が施されている。それまでの一般的なフラスクでは、蓋の部分は隠されていなかったのでフラスクであることは明白だった。こちらは、分厚い本に似せたカバーの中に、まるごとフラスクを仕込むので、フラスクであることがバレない。飲む時には、底部に指を突っ込んでボトル部分を押し上げて、上の開口部から飲み口が飛び出てくる仕組み。アルコールを人に悟られずに飲みたいという熱意が伝わる発明となっている。

キャッチャーがボールに触ることなくボールをキャッチしてしまうミット(1904年認可)
キャッチャーがボールに直接触れることなく、ボールをキャッチするための道具。図面を見れば分かる通り、長方形の網で覆われている。本体の5と6の部分の網目状の部分は内側に開く扉となっており、ボールが当たると、内側にボールが入るようになっている。ボールをキャッチすると、扉はバネの力で元に戻る。フレーム本体の奥にはクッションが内蔵され、クッションと奥のプレーヤー側の面の間にはバネが仕込んであるので、ボールがクッションに当たると、衝撃が吸収される。キャッチャーなのに手を使わなくていい点が斬新だ!

無線機つきショッピングカート(1964年認可)
ショッピングカートの故意または過失による持ち去りに対処しようと発明されたショッピングカート。ショッピングカート本体に無線受信機が付属しており、店から一定の距離を離れて無線が届かなくなるとショッピングカートのアラームが鳴り響く仕組み。また、無線受信機から、店や商品の宣伝情報を流すことも可能。カートから絶えず商品情報が流れてきたらそれはそれでうるさそうだ。
まだまだあります! Part2に続きます。乞うご期待!!