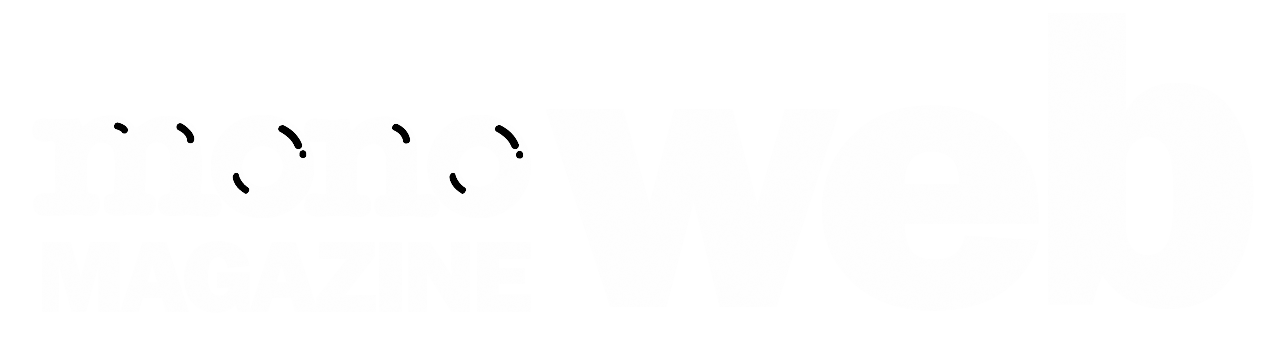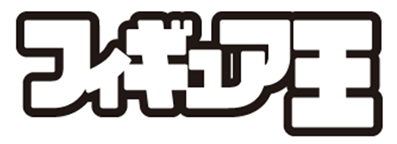構成/ワールド・ムック編集部 文/伊藤浩子
※米特許図面をもとに編集部が色を付けました。
Part1はこちら

自動の子豚餌やり装置(1964年認可)
生まれたてのかわいい子豚たちにまるでお母さん豚が母乳をあげるような感じで液状の餌を与える装置。装置自体が母豚を模した形になっていて、子豚に安心感を与え、なるべく自然に餌を飲めるように配慮。さらに、タンク内の餌の温度管理を行ない、設定された時間になると電気によってバルブが制御され、餌やり用のタンクに自動で餌が流れ込む仕組み。母豚の実際の鳴き声まで餌の時間になると流れる、究極の自動子豚餌やり装置だ。

ミシン(1858年認可)
針の動きに合わせたループ機構、布をスムーズに送るための部品、糸の張り具合を均一にするシステム、針の違う部分にループが発生するのを防ぐための機構などの新たな改良点を加えたミシンの発明だが、特許文を呼んでも、イラストに使われている馬がなんの役割を果たすのかまったく不明。馬の部分はフレームという名称で呼ばれているようだが、馬にミシンを操らせるのか、どうなのか、いっさい説明されていない。

銃発砲用装置(1921年認可)
強盗などから財産や身を守るための発明がこちら。この装置があれば、コートの下に見つからないように隠し持った銃を、両手を挙手したハンズアップ状態でも発射可能だという。銃はイラストに描かれているように着用者の右胸あたりにストラップで取りつけおき、トリガーを引くためのボタンは服の袖部分を通して右手の掌部分の指が届く範囲のところに位置させる。万が一、強盗に襲われ、両手を挙げさせられている時にも、ボタンひとつで銃を発射可能。1発目は誤発射に備えて空砲を仕込んでおき、2発目から実弾を入れておくという。

飛行船(1893年認可)
1893年に認可されたこちらの特許は当時人気を博し始めていた飛行船に関するものだ。特徴としては、シンプルで耐久性があり、かつ頑丈で、高速でプロペラが回転し、方向転換も簡単であるとしている。飛行船の歴史を紐解くと、最初に飛行船の試作に成功したのはフランス人で1852年のことだった。その後、1897年にユダヤ系ドイツ人のダーフィット・シュヴァルツが飛行船の飛行に成功。その特許を譲り受けたツェッペリンが1891年から飛行船の開発を始め、1900年に初飛行に成功し、有名なツェッペリン号を完成させた。こちらの特許ではニトログリセリンで推進力のもととなる爆発を起こさせる。空の旅は危険と隣り合わせだったようだ。

列車衝突回避装置(1888年認可)
大陸横断列車が開通し、広大なアメリカ大陸をオマハからサクラメントまで横断することができるようになった1869年から19年後に認可されたこちらの特許では、さまざまな障害物との衝突を回避する装置が提案されている。この装置は先行車として蒸気機関車の前に走らせるもの。伸縮性のある管でつながれた先行車により、列車にブレーキをかけたり、エンジンを逆回転させて停止させたりできる。先行車には運転手が操作することのできる人形が乗っており、牛などの動物に警報を発するため、備えつけのゴングを鳴らしたり、両手を挙げて脅かしたりすることもできるという。人も乗れると書かれているが、列車の前を走行するのはちょっと危険な気もする。

ニワトリ用アイプロテクター(1903年認可)
ニワトリがメガネをかけているかのようなイラストを見るとかなり滑稽だが、これは実はニワトリがほかのニワトリに目をつつかれないためのプロテクターなのだ。ニワトリの小さな頭にかけるため、すばやくつけたり外したりができること、ニワトリの視界を遮らないこと、そして大きさの異なるニワトリに対応できるよう、サイズを調節できることなどを考慮して考案されている。ただ、どうしてもニワトリに伊達メガネをかけて遊んでいるようにしか見えない。

ポケットブック(1883年認可)
こちらは、主に手袋をはめた淑女向けに考案された、小物入れをどこかに置き忘れないためのブックタイプの小物入れ。左手にはめた手袋の甲の部分にループ状になっている装置を取りつけ、ブックタイプの小物入れのほうにスナップ式のフックと器具を取りつけておき、手袋側に装着する。装置や器具はどちらも目立たないので、小物入れを手袋に設置していない状態でも目立たず、普段も手袋を着用しやすい。小物入れは中に仕切りがたくさんあり、切手や切符などこまごましたものを入れるのに適している。

ナプキンホルダー(1895年認可)
紙ナプキンなどなく、布製のナプキンを使用していた時代ならではのアイテムがこちら。シャツの襟ぐりや洋服にひっかけて使うナプキンホルダーで、一片の細長い金属シートを折り曲げて、裏側にナプキンを留めるためのピンチが取りつけてある。とてもシンプルなつくりで、誰でも作ることのできる点がウリ。図面の男性がとってもジェントルマンだ。

乳牛用ハエ防止マスク(1963年認可)
乳牛またはそのほかの動物の顔に装着できるようになっているプラスチック製のマスク。取り外しができ、マスクには目の細かい網目状のスクリーンが取りつけられている。網目が細かいので、牛は前を見ることができる一方、虫などから目を守ることができる。キャンバス地などでできたストラップを留めることで牛の顔にマスクを固定することができるようになっている。

口ひげガード(1901年認可)
口ひげに食べ物が付着するのを防止するためのとてもシンプルな器具、その名も口ひげガード。ベストのポケットに入れて持ち運ぶことができ、物を食べる時に簡単に口ひげに装着できるという。その仕組みは、弓形の本体にギザギザの歯がついていて、その歯をヒゲの毛に埋め込むように差し込むというもの。一瞬にして、垂れ下がっていた口ひげが上向きになるので、食べ物が付着するおそれがなく食事を楽しむことができる。ただ、装着している時の見た目が気になる。

自動車用アタッチメント(1930年認可)
こちらの発明は、前の車の人に話しかけるための道具だ。長い筒のような管の先に拡声器がついており、ドライバーは手前にあるマウスピースに向かって話しかける。発明者がうたっている通り、とてもシンプルで、特別な工事も必要としない。ただ、このようなボンネット設置型の拡声器が普及した形跡は残っていない。

フケ顔を最小限に食い止める方法(1952年認可)
顔の老化を、整形手術なしに、まったくなかったものにする、もしくは最小限に食い止めるための方法を記した特許がこちら。老化のサインとなる顔のしわやむくみ、たるみを消し去るべく肌を引っ張り上げる方法だという。が、その方法とは、ヘアピン状のものを頭皮に軽く差し込んで表面の皮膚を引っ張り上げるというもの。リフトアップがかなうとしても、これではかなり痛そうだ。

靴(1896年認可)
自転車に乗る時や歩行する時に適した靴を提案しているのがこちらの発明。足の甲を覆う部分が左右にパカっと開くので、足入れがしやすく、調節可能なので靴擦れが起こりにくいという。また、炎症性のリウマチにも言及し、その原因として長時間濡れたままの靴下や靴を履いていることを挙げ、そういった問題も解決できるとしている。今でいうコンフォートシューズだが、カチっとした靴しかなかった当時としては斬新だったに違いない。

モーター駆動車用アタッチメント(1904年認可)
自動車と馬車が同じ道路を走っていた1900年初め頃に考案された自動車が車道を走る馬を驚かせないための装置。その方法が斬新で、馬には馬を、といった感じで、車の前に馬を模したフィギュアをつけることを提案している。馬は実物大で、車のフロント部分に取りつけて車の動力を利用して、動かすことができるという。まるで生きた馬が車を引いているかのように見せかけるとしているが、はたして馬の目はごまかせたのか?

歩行者やほかの乗り物を安全に排除する装置(1932年認可)
自動車やトラック、路面電車など、対人事故を起こしたり、ほかの乗り物や壁などにぶつかったりする場合に役立つ装置。人にぶつかったとしても、装置先端部の棒状のものにまず当たり、そこから毛布またはゴムの薄いマットが飛び出てケガを防いでくれる。またワンクッション置くことで車の傷もつきにくい。現代のエアバッグの前身的な発明といえるのだが、図面を見る限り、この棒に当たるだけでもかなり痛そうだ。

宇宙船(1963年認可)
こちらは「NASAに権利を譲渡する」と明記されている、NASAの有人宇宙飛行に貢献したと思われる職務発明の特許。特許の請求項が17項目もあり、完全に理解するのは容易ではないが、ロケットで宇宙軌道まで飛ばし、ミッションを終えた後に無事に地球に帰還できるよう、大気圏再突入が可能なように設計された有人宇宙船だ。宇宙船の形は、月面着陸に成功したアポロ11号と酷似したデザインで、宇宙へのロマンを掻き立てられる。